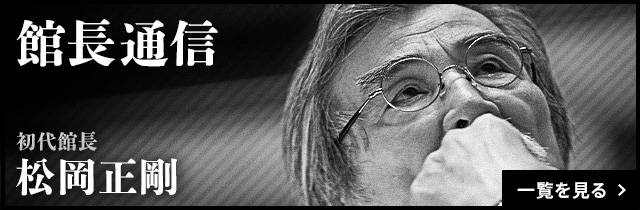館長通信
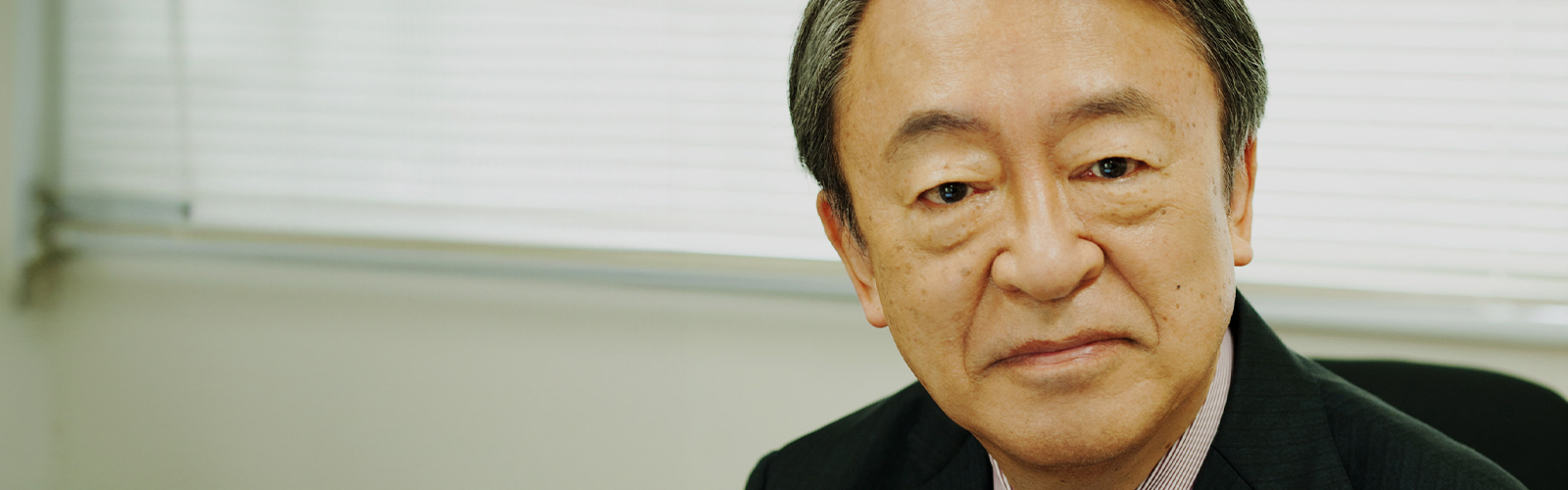
No.092025/09/15
「書くことの大切さ」が裏付けられた
私は複数の大学で講義を持っていますが、学生諸君の態度は千差万別。ほぼ全員の学生が教室にパソコンあるいはタブレットを持参し、私の講義内容を打ち込んでいくという大学もあれば、そもそもパソコンを持参しない学生ばかりという大学もあります。
パソコンを持参しない学生の反応もさまざまです。私が配布したレジュメに講義内容をメモする学生いれば、全くメモを取ろうとしない学生もいます。
こんな学生を見ると、私のやる気に火がつきます。学生が思わずメモを取りたくなるような講義をしなければ、という気になるのです。
その結果、学期初めは私の講義を聞くだけという態度をとっていた学生たちが突然メモを取り始めると、内心「やった!」と快哉を叫びます。
でも、メモを取ることと読解力や思考力には因果関係があるのかどうか。今年9月1日、一般社団法人応用脳科学コンソーシアムは、東京大学の東京大学大学院総合文化研究科の酒井邦嘉教授やNTTデータ経営研究所、日本漢字能力検定協会など複数の組織と共同で「筆記と読書の関係性」を検証して発表しました。
ジャーナリストというのは、なんでも素直には受け取らないもの。研究テーマを見ただけで、「筆記と読書には関係性がある」という結果を予想した研究ではないかと思ってしまうのですから困ったものですね。そして結果は、その通りでした。
発表のポイントは、以下の通り。〈大学等の講義内容の記録について、記録しないと回答した人は全体の10% に上り、日常的な予定の管理について、紙または電子機器に記入することがないと答えた人は全体の24% に上りました。一部の学生で書くことが習慣化していないという実態がうかがえます。
日常で本や新聞・雑誌を読む時間に関して、いずれも普段読まないと回答した人は全体の20% に上りました。日常的に紙の本を読むと回答した人でも、その読書時間は1日あたり40分程度にとどまっており、十分とは言いがたい状況です。
日常的に本や新聞・雑誌を読む人の方がより多様な場面で書く傾向にあり、多様な場面で書く人の方が本や新聞・雑誌をより長時間読む傾向がありました。また、講義内容を記録する人や、本や新聞・雑誌を普段読む人のほうが国語の読解問題の成績が高くなりました。つまり、書くことと読むことの累積効果によって、読解力が高まる可能性があります〉
なるほど、納得の結果ですね。でも、こういう調査結果の発表を見たり聞いたりするときには、どんな人が対象だったかも合わせてみる必要があります。きちんとした調査発表であれば、調査方法が明記してあります。この発表も明記しています。
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/info/news/topics/20250901140000.html
それによると、〈対象者は、アンケートモニター募集サイト「NTTコム リサーチ」に登録している学生であり、回答者には報酬として、サイト内ポイントを支給しました。居住地は全国にわたりますが、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県だけで84%を占めていました。所属は大学生93%、大学院生6%、短大生1%であり、男女の内訳は女性71%、男性28%、無回答1%です〉
これを見ると、「主に首都圏在住でインターネットを日常的に使用する女性を中心に尋ねたところ」というのが実態でしょう。男女比に大きな差が出たのが惜しまれます。
この調査では分析結果の詳細を資料として添付しています。それによると、〈大学等の講義内容の記録に関して、回答者1,062名のうち講義内容を記録することがないと回答した人は全体の10% (107名)に上りました〉
なるほど、大学で教えている私の実感と乖離してはいません。 〈日常で本や新聞・雑誌を読む時間に関して、回答者1,062名のうち本や新聞・雑誌いずれも普段読まないと回答した人は全体の20% (221名)に上りました。日常で本や新聞・雑誌(SNSは除く)を読むことと、メモや日記等の複数の場面で書くことの関連について、本や新聞・雑誌を読む人の方が多様な場面で書く傾向にあり、多様な場面で書く人の方が本や新聞・雑誌をより長時間読む傾向にありました。以上の解析結果で明らかになった大学等の講義内容を記録する人としない人について、国語問題の成績を比較したところ、前者の成績のほうが高いことがわかりました。また、本や新聞・雑誌を普段読む人は、いずれも全く読まない人より成績が高いことがわかりました。〉
はい、予想通りの結果になりました。そりゃそうだよね、というものです。というわけで、学生諸君、講義内容はしっかりメモを取りましょうね。
角川武蔵野ミュージアム館長
池上 彰