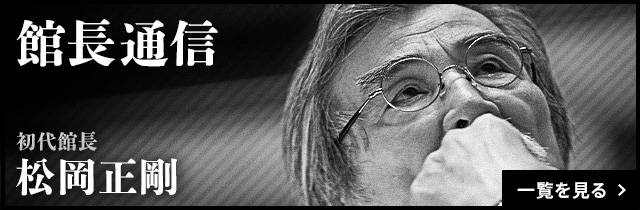館長通信
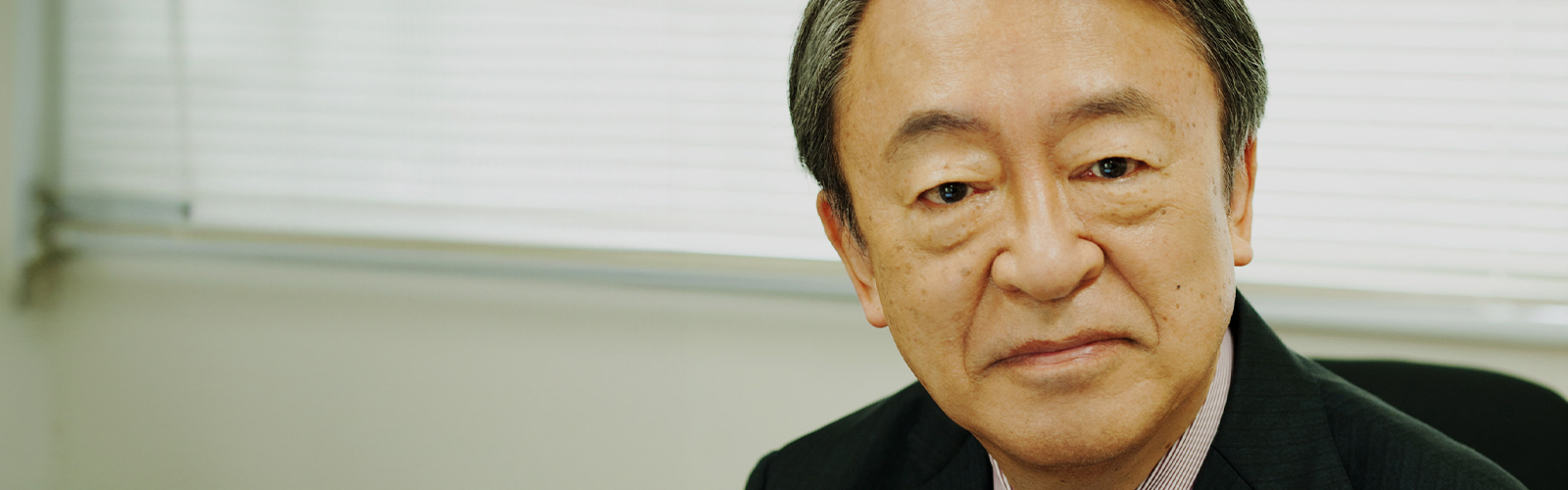
No.082025/08/15
戦後80年を考える
「八月や六日九日十五日」
これは戦争の犠牲者を悼む有名な俳句です。多くの人が似たような句を詠んでいるので、最初に詠んだ人は特定できないのですが、6日は広島に原爆が投下された日、9日は長崎、15日は終戦記念日です。8月は、戦争を思い起こす日が多いのです。今年は戦後80年。どんな気持ちで今年を迎えるのでしょうか。
「8月ジャーナリズム」という言葉があります。これは、「ジャーリズムはふだん戦争や平和について語ってこないくせに、8月だけは戦争を回顧する特集をする」という揶揄の表現です。
でも、せめて8月くらいは戦争の歴史に思いを馳せてもいいでしょう。この戦争を、もう一方の当事者のアメリカの人たちはどう考えているのか。最近アメリカの民間調査団体ピュー・リサーチ・センターが7月28日に発表した世論調査があります。アメリカによる広島と長崎への原爆投下について「正当化できる」と答えたアメリカの成人は35%、「正当化できない」と答えた人が31%と分かれています。ちなみに33%は「分からない」と答えています。
調査は今年6月の2~8日に18歳以上のアメリカ国民約5000人を対象に実施されました。
調査機関は異なるのですが、アメリカの世論調査会社ギャラップ社が原爆投下直後に実施した世論調査では、85%のアメリカ国民が投下を支持していましたから、原爆投下に否定的な人が増えていることがわかります。
今回の調査で18〜29歳では「正当化できない」が44%に上り、「できる」の27%を上回っていました。
これは大きな変化です。原爆投下直後、トルーマン大統領は原爆投下を正当化するために「原爆投下が終戦を早め、日米両軍兵士のこれ以上の犠牲を防ぐことができた」と主張しました。実際には日本は敗北を認める寸前で、原爆開発に携わったアメリカの研究者たちの中にも原爆投下に反対する人がいたのですが、トルーマンはソ連にアメリカの力を見せつけるために投下を強行しました。しかし、被爆から80年。被爆者団体の取り組みもあり、最近はアメリカ国内でも若者たちが原爆の悲惨さを知るようになってきています。日本の被団協(被爆者団体協議会)がノーベル平和賞を受賞したことも影響しているかもしれません。
その一方で、7月の参議院選挙では「核武装は安上がり」と主張する候補者が出ました。もし日本が核武装をしようとしたら、「核拡散防止条約」違反として各国から経済制裁を受けることになり、原子力発電所用の燃料のウランが輸入できなくなるという現実を、どこまで理解してのことなのか。もし核兵器を開発しても、核兵器の爆発力を確認するための核実験をする場所が日本国内にあるでしょうか。
日本が核兵器を持つことは、モラルとしてだけではなく、現実にできないというリアルな考え方ができない政治家がいることには愕然とします。
たしかにロシアのプーチン大統領がウクライナ侵攻に際して核を脅しに使ったりするのを見ると、核兵器廃絶は遠い理想に見えますが、時と共にアメリカの若者たちの意識が変わってきたのです。
そこで、私はある被爆者の言葉が忘れられません。
「私たちの取り組みは微力ではあるが無力ではない」
角川武蔵野ミュージアム館長
池上 彰