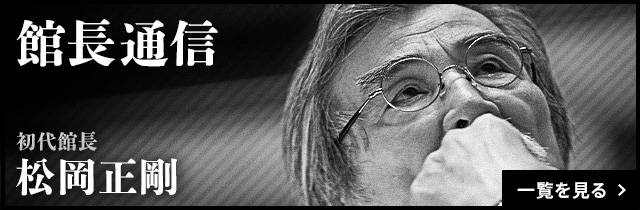館長通信
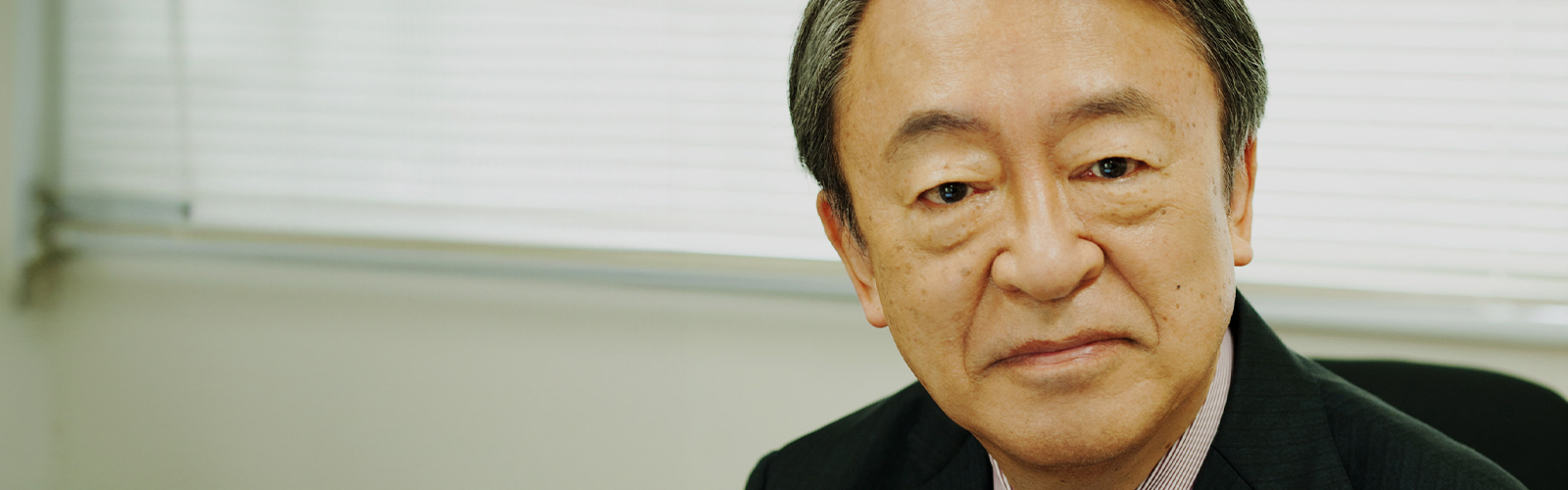
No.102025/10/15
現代版「焚書運動」が活発化
アメリカの作家レイ・ブラッドベリが1953年に発表した未来小説『華氏451度』は、紙が自然発火する温度を書名にしました。書物が禁止され、発見された書物はすべて焼却されるようになった近未来の世界を描きました。まさに「焚書」です。当時のアメリカでは、東西冷戦の中で共産主義に対する恐怖が広がり、共産主義者と疑われた者は公職から追放されるという「赤狩り」の時代でした。
その一方で、アメリカと対立していたソ連でも思想の自由がなくなっていました。
こんな未来が来てはならないという思いで書かれた書物ですが、いまのアメリカでは現代版「焚書」とでもいうべき事態が広がっています。気に食わない書籍を図書館で閲覧禁止にしようという運動です。対象になった書籍は、人種やジェンダー、多様性に関するものです。
この動きが大きくなったのは、2020年にジョージ・フロイドという黒人が警察官の暴力によって死亡するという事件がきっかけです。当時のアメリカで「ブラック・ライブズ・マター」(黒人の命も大切だ)という運動が広がりました。その過程で、学校でアメリカの黒人差別の歴史を教えるところが増えたとされます。これに反発する保守的な白人の親が、「アメリカは偉大な国だ。学校でアメリカの負の歴史を教えるな」という運動を始めます。学校の図書館や公共図書館で黒人差別の歴史を扱った本を読めないようにしろという運動が全米に拡大したのです。
それが次第にエスカレートし、「神様はアダムとイブを御創りになった。つまり世の中には男と女しかいないのだからLGBTQを扱った書物は閲覧禁止にしろ」という主張にもなったのです。過去のアメリカでは、聖書の記述に反するとしてダーウィンの『進化論』が禁書になった地域もありました。さすがにいまはなくなりましたが、こうした流れが続いているのです。
このような「草の根の保守」の運動が、トランプ大統領を当選させる駆動力にもなったのでしょう。
誰でも読みたくない本はあります。でも、それを人に押し付けるのは筋違いでしょう。公共の図書館は、誰でも自由に多種多様な意見や思想の書物に接することができるから価値があるのです。
当ミュージアムは公共図書館ではありませんが、「公共性」の大切さを常に意識しています。
実は日本でも戦時中は国策に沿わない書物が禁書とされた歴史があります。第二次世界大戦が終わってからも、今度はGHQによって禁書とされた書物があるのです。過去を振り返り、二度と過ちを犯さないという決意を持って、近々、当ミュージアムで、過去に禁書とされた本の展示を始める準備をしています。
この展示を通じて、本が自由に読めることの大切さを知っていただきたいと思います。
角川武蔵野ミュージアム館長
池上 彰