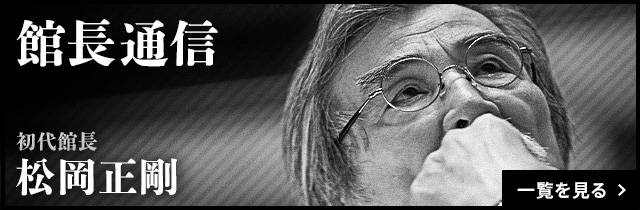館長通信
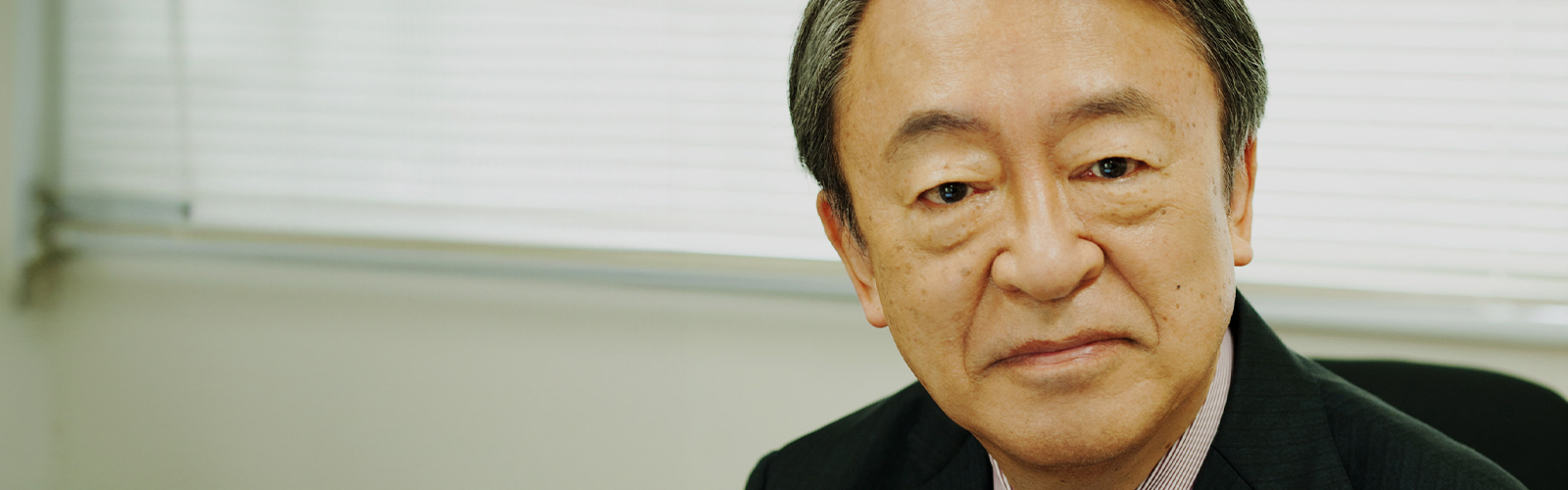
No.072025/07/15
昭和100年を考える
今年は昭和が続いていたとすると昭和100年に該当します。テレビをはじめさまざまな場所で「昭和100年」を記念するイベントが開かれています。当ミュージアムも4階にて「昭和100年展」を開催しています。
100年もの長い期間のどこを取り上げるか。いろいろな視点がありますが、この展示では、戦後の復興を経て高度経済成長期に入った昭和40年(1965)に焦点を当て、当時の社会や人々の暮らしを紹介しています。
展示室内では、当時の暮らしを追体験できる昭和40年の一軒家を再現しました。表札には「池上」と書かれています。当時の池上家も、こんなものでした。手がけたのは映画『ALWAYS 三丁目の夕日』の美術を担当した上條安里氏です。
当時、館長の私は東京都内に住む中学校3年生でした。前年に東京オリンピックが開かれ、貧しかった日本が次第に豊かになり始めた時期でした。室内には当時「三種の神器」と呼ばれた白黒テレビ、冷蔵庫、洗濯機のうちの2つがあります。
テレビのCMで消費意欲が掻き立てられ、冷蔵庫でアイスクリームが保存できて、ビールなどの飲料を冷やすことができることで、「冷えたビールはこんなにおいしいのか」と消費が爆発的に拡大。牛乳などの乳製品も保存でき、経済が発展するきっかけとなったのです。この家庭では、まだ洗濯機が購入できず、外のたらいがかけられていますが、洗濯機が入ると、主婦の家事労働が軽減され、外で働く女性が増える原動力にもなりました。この一軒家を子細に見ることで、高度経済成長直前の日本の庶民の暮らしがわかるのです。
会場には親子三代の客も目立ちます。おじいちゃんやおばあちゃんが、「そう、そう、こんな風になっていた」と得意げに孫たちに説明する光景は微笑ましいものです。
庭にはメンコなども用意しました。子どもたちに、どんな風に遊ぶのか実演してはいかがでしょうか。
子どもたちからは「昭和に行ってみたい」という声が出るかもしれませんが、当時を知る大人たちからは、「いまだからこそ懐かしく思えるが、当時は生きるのに必死だった」という感想も出ることでしょう。時代によって異なる「昭和感」。昭和の歴史的意味を考えるひとときをご体験ください。
角川武蔵野ミュージアム館長
池上 彰