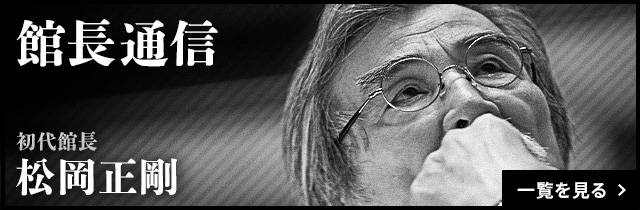館長通信
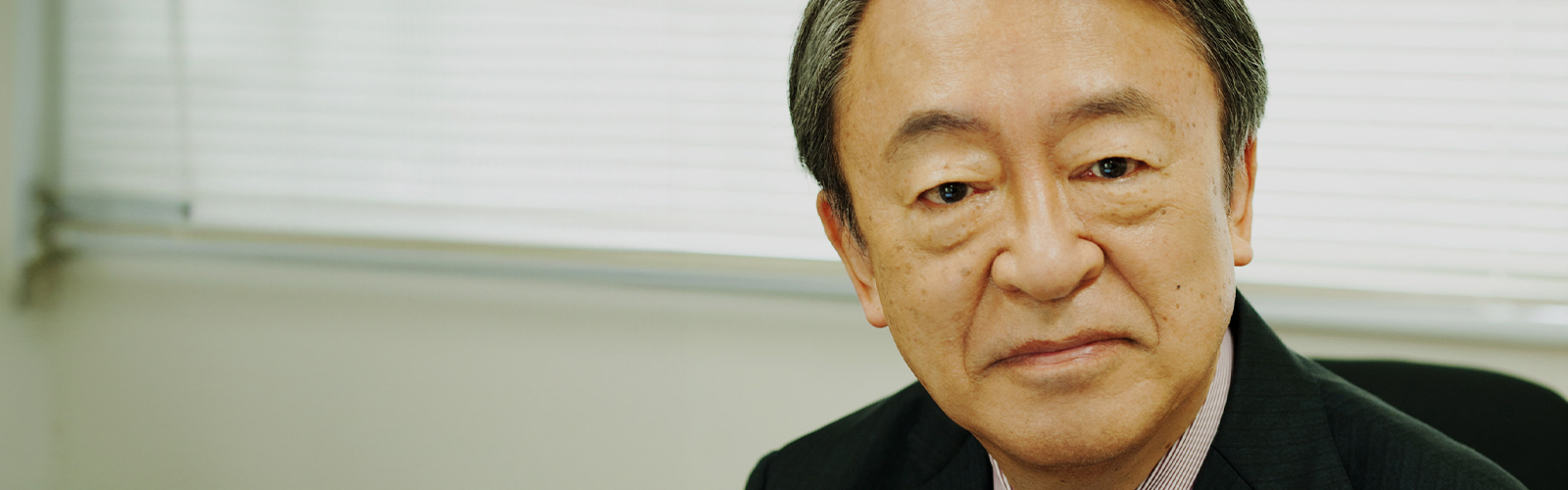
No.042025/04/15
浮世絵ブーム再び
当館のモネ展は終わってしまいましたが、連日大勢の人に来ていただいています。春休みということもあるのでしょう、子どもたちが熱心にページを繰っている姿を見るのは楽しいものです。当館の横の川沿いの桜も3月末から満開になりました。
既に発表していますが、4月26日から「浮世絵 RE:BORN」と題した展示が始まります。「時を超えたジャポニズム 体感型デジタルアート劇場」です。現在は鋭意準備中。未完成ではありますが、現時点で見ても、その素晴らしさに圧倒されます。
浮世絵に詳しい人でしたら、「ああ、ここは広重の絵だな。おお、ここで写楽が登場か」などと楽しめますが、浮世絵師の名前に詳しくなくても、絵そのものが持つ力を感じてください。
絵に詳しくない人のためには私の音声解説が用意されています。でも、最初は私の解説など聞かずに、絵と音のダイナミズムを全身で体感することをお勧めします。二回目以降に音声解説を聞きながら体感していただくと、より理解が深まると思います。要は何度も来てください、ということなのですが。
おりしもNHKの大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」が放送中で、これを機会に浮世絵に興味・関心を抱いた人も多いことでしょう。モデルになった蔦屋重三郎は江戸時代中期から後期にかけて活躍した版元です。曲亭馬琴、喜多川歌麿、葛飾北斎、東洲斎写楽など多数の浮世絵師の作品刊行に携わっています。
極端なことを言えば、蔦屋重三郎がいなければ、浮世絵ブームは起きなかったかも知れないのです。専門家の中には、現代で言えば蔦屋は出版社であり編集者であり、プロデューサーでもあったと評する人もいます。「江戸のメディア王」との異名もあります。
そう考えると、いささか我田引水ではありますが、角川書店を創業した角川源義も、国文学者で俳人で角川書店創業者として、数多くの作家や俳人を世に送り出してきました。その思いを継いだのが、このミュージアムではないかと思っています。
江戸時代を発掘し、現代のアートとして楽しむ。4月26日からの展示に期待してください。
あ、そうそう。その頃だと当館は一段と賑わいますから、その前にお越しいただいて、館内を楽しんでいただければと思います。
角川武蔵野ミュージアム館長
池上 彰